「フィッシュアイ」という言葉を聞いたことがありますか。
パン生地を焼成した時に↓↓の写真のように表面にぶつぶつと空気が入ったような症状の事です。


フィッシュアイの原因は?
①生地中の温度差
②生地の冷凍障害
①生地中の温度差
フィッシュアイが起きる原因として、一番多いのは生地中で温度差が生まれることです。
基本、どんな生地でも1日の中で「ミキシング→1次発酵→分割→成形→2次発酵→焼成」と工程が進む場合、フィッシュアイは起きにくいです。
菓子パンや食パン、バゲットなど、材料や発酵時間が違う生地でも「フィッシュアイ」が起きることはほとんどありません。
しかし、生地の種類に関係なく、低温長時間発酵をさせた生地では「フィッシュアイ」が起こりやすくなります。
低温長時間発酵は冷蔵庫や低い温度帯で長時間発酵させるので、生地中の温度が下がってしまいます。
その生地が冷えた状態で、成型→発酵→焼成などと工程が進むと、フィッシュアイが出やすくなります。
生地の中心から外側まで生地温度が均一にならず、差が出来てしまうと、焼成時に火ぶくれのようにフィッシュアイができやすくなります。
またベーグルのように「ケトリング」という茹でる工程があっても、温度差が均一になっていなければ、↓↓写真のように「フィッシュアイ」は起きることもよくあります。

②生地の冷凍障害
これはミキシング後分割して「冷凍、解凍する環境によって生まれる冷凍障害」です。
「冷凍、解凍の途中で生まれる温度変化によって、グルテン形成が変化してしまうこと」や「冷蔵庫や冷凍庫のドアの開閉によって、結露したり水分が溶けたり、再度凍ったりして、組織が壊れること」などが原因にあげられます。
また、これは私自身の経験上の話ですが、冷凍生地を作って1日目(翌日)に使う時と、3日目に使う時と比べた時、3日目の生地に「フィッシュアイ」が起きやすい傾向があります。
もちろん、時間が経てば経つほど、イーストの発酵力が弱まり、ふっくらとしたパンができにくくなりますが、その問題とこのフィッシュアイが関係しているかは正直、今のところわかりかねます。
冷凍生地を使うことで効率が良くなる一面もありますが、イーストを練り込んだ生地を「冷凍・解凍」することで、色々な良くない現象も起きてしまいます。
この色々な良くない現象をまとめて冷凍障害と言います。
解決策
生地中に温度差が生まれることで起きる「フィッシュアイ」の解決策として生地温度を均一に戻すということです。
そのため、解凍後、復温したり、(分割)丸めなおしたり、ベンチタイムをとったりといくつか工程を踏むことで、均一に温度を戻すことができます。
この焼成までの時間でしっかりと生地温度が均一になれば、フィッシュアイができにくくなります。
生地の冷凍障害に対しては、出来るだけ、「急速冷凍庫で一気に冷凍すること」や「-15℃くらいの温度帯をキープすること」などで、発酵が始まる前にしっかり中心まで生地を凍らすことができますし、またドアの開閉などで生まれる結露や結晶化を防ぐことができます。
また、冷凍耐性のあるイーストを使うことも1つの解決要因になります。
食感や味に変化があるのか?
食感の変化に関しては、生地の種類にもよりますが、多少は変わります。
やはり、大きい気泡やたくさんのフィッシュアイが出てしまうと、そこが薄く膜のようになったり、またハード系などではそこだけ、硬くなったりすることもあります。
味の変化については、正直そこまで変わりません。
発酵不足や過発酵などでは食感の変化もそうですが、発酵臭が強くなったりして、食べた時に、少し嫌な感じがすることもありますが、しっかりと焼成時に膨らんで(窯伸びして)入れば味の変化は正直感じられません。
一流のブランジェや本当に味覚がしっかりと感じられる人でない限りなかなか判断ができないとおもいます。
・ケトリングについて
・モルトについて

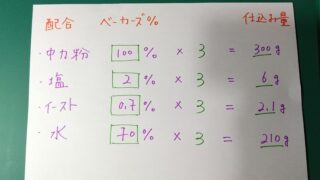
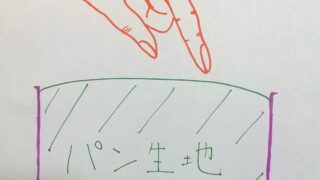






コメント