パン作りに絶対欠かせない材料の1つが「イースト」です。
イーストには、スーパーで買える「インスタントドライイースト」、専門店で買える「生イースト」、パン屋さんや外国ではよく使う「ドライイースト」それから自分で作る「(自家製)天然酵母」の4つがあります。
今回はその中でも一番よく使う「インスタントドライイースト」とパン屋さんでよく使う「生イースト」の2つに絞って話していきます。
また、生イースト⇔インスタントドライイーストの換算方法についても説明します。
・「牛乳とスキムミルクの換算方法」についてはこちら↓↓
生イーストとインスタントドライイーストの違い
生イースト

「生イースト」とは、パン作りに適した菌を培養して、水を切って固形にしたものです。
「水を切った」といっても乾燥させているわけではないので、ボロボロとした豆腐のような状態です。
薄茶色のような色をしていて、豆腐のようなブロック状態で売られています。
生イーストの特徴
- 賞味期限が短く、冷蔵庫でのみ保存ができる
- 糖分の分解が早く、耐糖性がある
- 焼成後に甘い香りとふわふわ食感になる
1、賞味期限が短く、冷蔵庫でのみ保存ができる
賞味期限は未開封の状態で2週間程度で、開封後は2~3日で使わなければいけません。
保存方法は冷蔵庫のみで、常温保存や冷凍保存はできません。
常温保存してしまうと、発酵がスタートしてしまい、発酵臭がしはじめたり(腐る)、発酵力が弱くなったりと、パン生地に使えなくなってしまいます。
冷凍庫で保存してしまうと水分が膨張して、細胞が壊れてしまい、きちんと発酵しなくなってしまいます。
生イースト本体を冷凍保存することはできませんが、パン生地に練りこむと冷凍することができます。
そのため「冷凍生地玉」などと呼ばれる、事前に生地を仕込んで、冷凍し、使いたい時に「解凍→成形→焼成」ができる生地を作る際にも使えます。
・「冷凍生地玉」レシピはこちら↓↓
・バター生地
・「ミルヒブロート」レシピ
2、糖分の分解が早く、耐糖性がある
生イーストは糖分の分解が早い特徴があります。
イーストはパン生地中の糖分を餌として、発酵します。
この糖分を分解するのが早いため、短い時間でパンを膨らます(発酵する)ことができます。
また、生イーストには耐糖性に優れています。
イースト発酵には糖分が必要ですが、逆に糖分が多すぎると浸透圧でイーストの細胞水分が活動が鈍くなってしまい、発酵力が弱くなってしまいます。
生イーストは耐糖性に優れているので、糖分が多い生地でも、イーストの活動が鈍くならず、きちんと発酵させることができます。
3、焼成後に甘い香りとふわふわ食感になる
焼けたパンをちぎって、断面を嗅いでみると、すごく良い香りがします。
この良い香り(パンの香り)がイーストで発酵させたパン生地を焼成した時に出る香りです。
ベーキングパウダーで膨らましたパン(生地)を焼成した場合、見た目は大きく膨らんでいますが、この独特な良い香りはありません。
また、もし生イーストを使って長時間発酵パンを作ると、糖分を分解しすぎてしまい、スカスカになり、香りも発酵臭(鼻につくアルコール臭)が強くなります。
そのため生イーストは短時間(適切な時間)で発酵させることで、よい香りでフワフワな食感が生まれます。
インスタントドライイースト
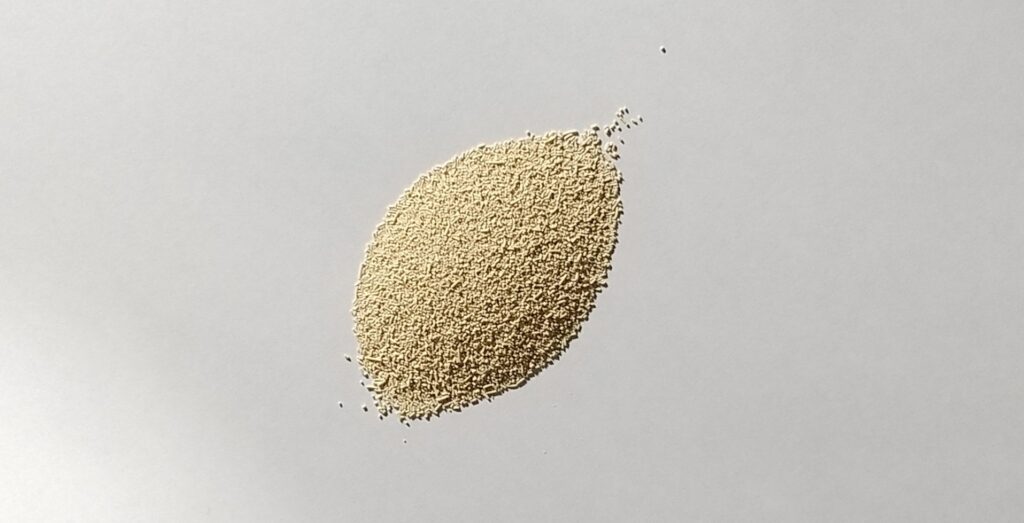
インスタントドライイーストは粉に直接混ぜ入れ、パン生地を作ることができるイーストです。
「ドライ」と名前がついてる通り、水分がなく、ふりかけのような細かい顆粒状です。
また専門店に行かなくても、スーパーで簡単に買うことができ、家庭で一番、使われているイーストです。
・インスタントドライイーストの特徴
- 賞味期限が長く、常温保存ができる
- 通常のものと、耐糖性があるものと2つある
- 長時間発酵が可能で、粉のうま味を引き出せる
1、賞味期限が長く、常温保存ができる
販売しているメーカーが多く、商品によって異なりますが、基本、未開封の状態で1~2年、開封後は1か月ほどです。
未開封の状態では常温保存ができるのが特徴です。
開封後は冷蔵庫で保存します。
頻繁に使わない場合は冷凍庫での保存も可能です。
しかし、インスタントドライイーストは湿気に弱いので、しっかりとジップロックなどに入れて、保存するようにしましょう。
2、通常のものと、耐糖性があるものと2つある
インスタントドライイーストは通常のものと、耐糖性があるものと2つあります。
通常のものは、スーパーで買えて、一番家庭で使われているイーストです。
耐糖性があるものは、スーパーにはなく、専門店で買うことができます。
バゲットなどの砂糖(糖分)が少ない生地には、通常のものを使います。
菓子パン生地やブリオッシュ、デニッシュなどの糖分が多い生地には、耐糖性があるものを使います。
生地中に糖分が多いと浸透圧によって、イーストの細胞が壊れて、きちんと発酵しなくなります。
この細胞壁が強く、簡単に破壊されないのが耐糖性があるイーストの特徴です。
3、長時間発酵が可能で、粉のうま味を引き出せる
特にバゲットやカンパーニュなどのハード系のパンは、材料がシンプルなため、1つ1つの工程が重要になります。
その重要な工程の1つに発酵(時間)があります。
シンプルな材料だからこそ、小麦粉の味がよくわかります。
その小麦粉のうま味を引き出す方法の1つが「長時間発酵」です。
生地を長時間発酵させることで、小麦粉が熟成して、うま味が増します。
バゲットの発酵時間は短くても90~120分。
長ければ「オーバーナイト法」を使えば、8~12時間程度です。
生イースト使用の「菓子パンや食パン生地」などは60~90分くらいが一般的な発酵時間です。
「インスタントドライイースト」は糖分の分解が遅く、発酵力が長時間続く特徴があります。
そのため発酵時間が長い生地に関しては「インスタントドライイースト」を使って、ゆっくり発酵/熟成されることで、粉のうま味が強くなり、美味しいパンを作ることができます。
・「オーバーナイト法」とその他の「パン作りの製法」についてはこちら↓↓
生イーストとインスタントドライイーストの配合換算
生イーストとインスタントドライイーストの換算方法はとても簡単です。
1つ、注意点としては、水分量です。
生イーストには水分が含まれています。
しかし、インスタントドライイーストは水分のない、顆粒状です。
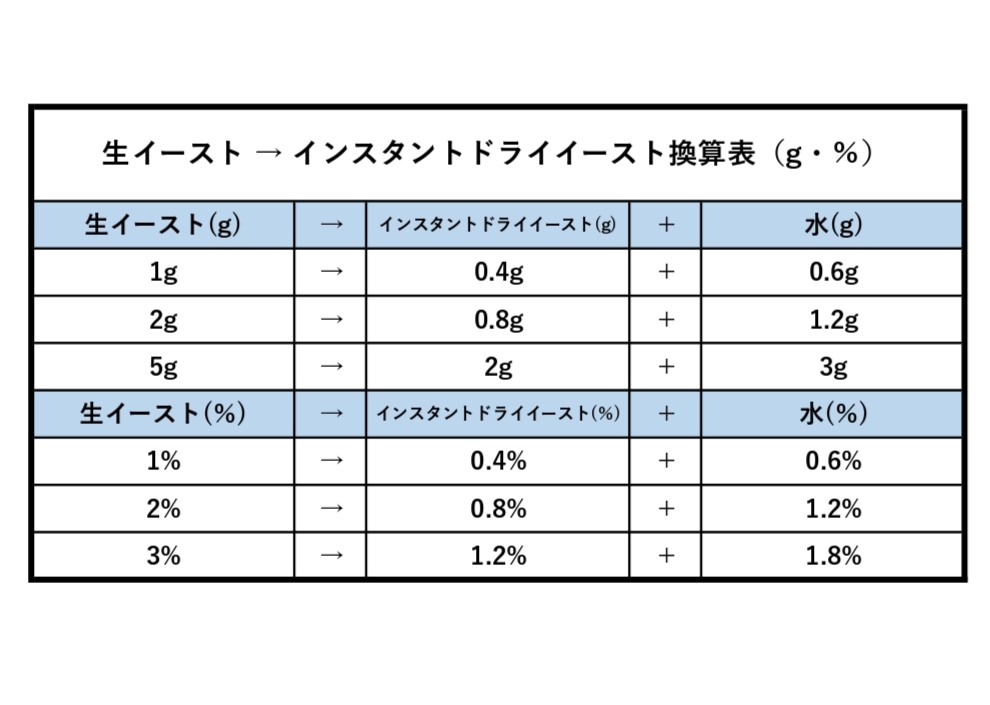
実際のレシピで見ると、もっとイメージしやすいかと思います。

まとめ
これが「生イーストとインスタントドライイースト」の特徴と違いです。
同じ「イースト」ですが、それぞれ、違う特徴があり、向いているパン(生地、製法)があります。
基本、家でパンを作る時は「インスタントドライイースト」を使うと思います。
スーパーで簡単に買うことができ、賞味期限も長く、保存もでき、1、2回で使い切る必要ないので、とても便利です。
もし、専門店で「生イースト」を買って来て、使う場合は、換算表を見ながら、計算してみてください。
水分量の調整だけを忘れなけばOKです。

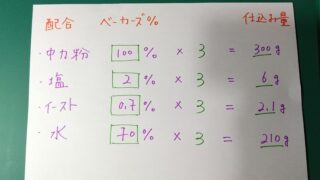
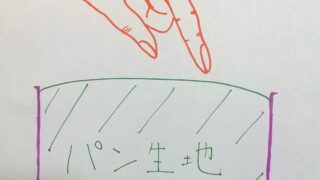








コメント